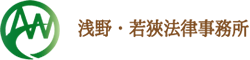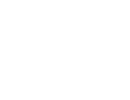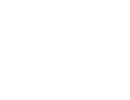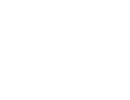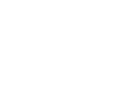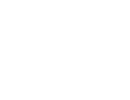損害賠償額が妥当かどうか。
治療終了後や後遺症認定後に保険会社の提示する金額で示談しても良いかどうかわからない場合、ご相談いただければ、提示金額が妥当なものかどうかアドバイスをすることができます。
また、弁護士が代理人となって賠償交渉をすることで賠償額が増額になることがあります。
治療終了後、後遺症14級の認定が出て、保険会社から90万円の示談案を提示された。弁護士に相談して、保険会社と交渉してもらったところ、170万円まで増額した。早めの解決を希望していたので、この内容で示談して、早期に支払ってもらった。
後遺障害の申請
保険会社から示談案を示されても、損害額が妥当なものかわからないときに、弁護士に相談することで、後遺症の可能性があるかどうかもアドバイスを得ることができます。弁護士に後遺症の可能性を見てもらい、後遺症が認められそうなときに、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺症の申請をすれば、後遺障害等級が認められることがあります。後遺障害等級が認められた場合、それまでの示談案に後遺症の損害もさらに加算されることになります。
依頼者は女性であるが、治療終了後、保険会社から110万円の示談案を提示されていた。妥当な金額かわからなかったので、弁護士に相談したところ、醜状痕があったが、後遺症の申請がされていなかったことから、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺症の申請をしたところ、自賠責では後遺症14級が認められた。その後、14級を前提に弁護士が代理人となって交渉したが、交渉では妥当な金額での提示がなかったことから、訴訟を提起し、裁判で500万円の和解をして、保険会社から支払ってもらった。
後遺症の認定に納得のいかない場合
後遺症の認定に納得がいかない場合でも異議申し立てができます。弁護士に相談して、異議申立が認められそうかどうかアドバイスを得ることができます。また異議申立の資料を弁護士に作ってもらったり、手続きを代わって行ってもらうことができます。
交通事故に遭い、むち打ち症になって、首に痛みが残ったため、後遺症の申請をしたが、非該当で、保険会社から示された示談案は50万円だった。しかし、納得がいかなかったので、弁護士に相談をしたところ、事情を聴取した書面を作成してもらい、後遺症の異議申し立てをしてもらった。そうしたところ、14級の認定が出た。そして、弁護士に代理人になってもらって、14級を前提に、170万円で示談をしてもらった。
保険会社の担当者とのやり取りが不安な場合
交通事故で治療中に相手保険会社の担当者とやり取りをする必要があります。そのときに、いろいろな書類を書いてほしいと言われることが多いですが、どのようなことになるのかわからず、不安になってしまうことがあります。あるいは不信感を感じることもあります。そういった場合に、弁護士が間に介入することで、保険会社の意図やその対応について、適切にしてもらうことができます。
交通事故で重傷を負ったが、保険会社から何度も同意書を書いてほしいと言われ、書いたらどのようになるのか、聞いてもよくわからなかった。また、治療状況や治り具合を何度もしつこく聞かれて、電話に出るのが嫌になってきた。そういう場合に弁護士に代理人になって、交渉してもらうことで、書類にどのような意味があって、対応したほうがいいのかどうかをアドバイスを受けることができた。必要な同意書などは書いたほうがスムーズに運ぶとアドバイスを受け、必要なものは納得してサインできた。また、治療途中の場合に今後の展望などを説明してもらい、不安が解消した。
自賠責の被害者請求
加害者が任意保険に加入していない場合または保険会社が治療費を支払ってくれない場合、被害者から自賠責保険に被害者請求をすることができます。もっとも、被害者請求には、多数の書類が必要なため、内容が難しくて理解できない方や仕事で忙しい方では、手続を行うことが困難なことがあります。
その場合、弁護士が代理人となって、被害者請求の代理手続ができます。弁護士が代理手続を行うことで書類の収集や保険金のスムーズな受け取りが可能になります。
相手が無保険だったため、自分で自賠責の手続きをしようとしたが、請求書の記載の意味がわからず、どれを出せばいいのかわからなかった。そこで、弁護士に依頼して、請求書を代わりに書いてもらい、必要な用紙をもらって、病院や会社に提出して、書いてもらい、弁護士のほうから被害者請求をしてもらった。
弁護士費用特約
弁護士に依頼する費用に不安がある場合でも、自動車保険に弁護士費用特約をつけてあれば、弁護士の費用を保険会社から支払ってもらうことができます。多くの場合これで、弁護士費用の自己負担がなくなります。
当事務所であれば、上記の具体例のいずれの場合でも、弁護士費用特約があれば全額弁護士費用を保険会社から支払ってもらい、自己負担はありません。
なお、当事務所では、相手方保険会社によっては受任できないことがあります。
まずは、ご相談ください。
 交通事故 Q&A
交通事故 Q&A
一覧を見る
- 1. 保険会社から損害提示を受けましたが、よくわかりません。
- 2. 治療費の支払いを打ち切られたのですが、どうすれば良いでしょうか。
- 3. 症状固定とは何ですか。
- 4. 症状固定後の治療費は全く支払われないのですか。
- 5. 入院時や通院時に付添したとき、付き添いの費用は賠償されないのですか。
- 6. 家屋の改造費用は認められないのですか。
- 7. 休業損害とは何ですか。
- 8. 後遺障害等級認定に納得がいきません。
- 9. 傷害慰謝料は、どのように算定されるのですか。
- 10. 後遺障害逸失利益とは何ですか。
- 11. 後遺障害慰謝料とは何ですか。
- 12. 死亡慰謝料はどれくらいですか。
- 13. 保険会社主張の過失割合に納得がいきません。
- 14. 裁判になった場合、どれくらいの期間がかかるのですか。