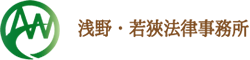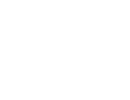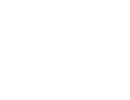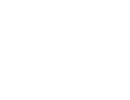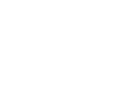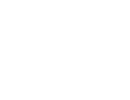遺産分割がまとまらない場合
遺産分割協議が当事者の話し合いでまとまらない場合、弁護士に依頼をして、調停などで遺産分割をすることができます。遺産分割協議や遺産分割調停でも弁護士がいない場合、法定相続分や特別受益、寄与分などの法的な規定の知識がないことで一方的に不利な分割案で了解するよう要求されることがあります。しかし、弁護士に依頼することで法的に妥当な分割案で交渉することができます。
兄弟3人が相続人で、遺産分けの話し合いをしようと持ち掛けていたが、以前から折り合いが悪く、全く話をしてくれず、そのままになっていた。そうしたときに、弁護士に依頼をして、遺産分割調停を申し立ててもらい、家庭裁判所から呼び出しをしてもらい、裁判所で話し合いをして、調停を成立させて、遺産分割をすることができた。
遺言書作成
遺言書を作成したいと考えているけれども、どうすればいいかわからない。そのような場合に弁護士に依頼をして、遺言書を作成してもらうことができます。
自分の財産を子供ではなく、自分の身の回りの世話をしてくれた甥にも上げたいと考えていたが、遺言書をどのようにすればいいかわからなかった。弁護士に相談をしたところ、子供にも財産を幾分か相続させて、甥には遺贈をすることができることを教えてもらい、弁護士が案文を作成した。案文で納得が言ったので、その内容で公証役場で公正証書遺言を作成してもらった。
遺贈寄付
遺言によって、自分の財産を死後にNPO法人や公益的な活動をする団体に寄付することができます。遺贈寄付のため、遺言書作成や遺言執行者の指名などをすることで確実に寄付することが期待できます。
自分には相続人がいないため、死後に社会のために役立ててもらいたいと、遺言書を作成しておくことで、ボランティア団体に自分の財産を寄付することができます。
遺留分
自分も相続人であるはずなのに、遺言があり、何ももらえなかった。そのような場合に、弁護士に依頼をして、遺留分の権利を主張して、相続財産の一部を取得することができます。
父が亡くなり、自分と妹2人が相続人だったが、父が遺言で、妹2人に全ての財産を分けてしまい、自分はもらえなかった。そうしたときに、弁護士に依頼をして、遺留分の権利を主張してもらい、相続財産のうち6分の1に相当する金銭を取得できた。
 相続 Q&A
相続 Q&A
一覧を見る
- 1. 相続の流れを教えてください。
- 2. 誰が相続人になるのでしょうか。
- 3. 相続分を教えてください。
- 4. 遺産分割はどのようにすればいいのですか。
- 5. 相続人の一人が遺産分割協議書を持ってきて、もうこうなるからハンコを押せと言われます。押さなくてはいけないのですか。
- 6. 生前に一部の相続人が生前贈与を受けていた場合でも相続財産は相続分通りに分けなければいけないのでしょうか。
- 7. 寄与分とは何ですか。
- 8. 遺産分割前の預貯金の払い戻しはできますか。
- 9. 相続放棄とは何ですか。
- 10. 限定承認とは何ですか。
- 11. 遺言書は作成したほうが良いでしょうか。
- 12. 遺言書にはどのような種類があるのですか。
- 13. 自筆証書遺言とはどのようなものですか。
- 14. 公正証書遺言とはどのようなものですか。
- 15. 秘密証書遺言とはどのようなものですか。
- 16. 遺言書で1人の相続人が全財産を相続した場合、何ももらえないのでしょうか。