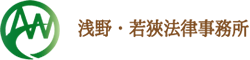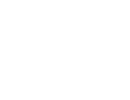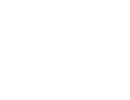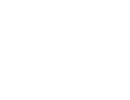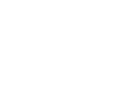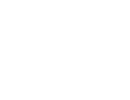貸金を返してくれない場合
貸金の催促をしてもなかなか払ってくれない。そのような場合に弁護士に依頼をして、交渉で返済合意をして、返済してもらったり、返してくれない場合には訴訟を起こして、返済を求めることができます。弁護士が入っていない場合、相手はなかなか返済をしてこないかもしれないですが、弁護士が入って、しっかり返済計画を立てて、文書を取り交わすことで約定どおりの返済をしてもらうことができます。
知人に必ず返すからと言われて貸した300万円について、返済を求めても、今月返すなどと言いながら、結局、返さず、再度催促したらまた翌月返すと繰り返すばかりで全然返済をしてくれない。弁護士に依頼をして、交渉してもらったが、相手が返してこないので、訴訟を提起して、和解をして返済してもらった。
取引先が苦しいと言って売掛金を返済してくれない場合
取引先が資金繰りが苦しいと言って、売掛金をなかなか支払ってくれないことがあります。従業員が電話や訪問をしていますが、なかなか支払ってくれません。そのような場合に弁護士が代理人として交渉して、返済計画の合意をして、毎月の返済をしてもらいます。そうすることで、今後、毎月一定の返済が期待できます。無理に一括返済をしても事実上、相手は返済できず、ときには倒産してしまうことがありますので、一定の毎月の返済をしてもらうほうがこちらにとっても得になります。また、回収手続きをとらないことで、消滅時効や相手方の倒産などの場合がありますので、早期の対応が肝要です。
売掛金が300万円滞納していて、苦しいと言って、なかなか返済してくれない。弁護士が代理人になって、交渉したところ、毎月5万円の60回払いであれば可能とのことであったので、分割返済の合意をして返済をしてもらうことになった。時間はかかったが、5年後には完済してもらった。
代金額に争いがある場合
代金額に争いがあって、取引先が支払ってくれない場合、弁護士に相談をして、相手の言い分の法的な根拠の有無、訴訟での見通しのアドバイスを受けることができます。また、弁護士が代理人となって、交渉または訴訟をすることで、相手から支払ってくれることがあります。
相手が売却した商品に問題があると言って、代金を全く支払ってくれない。そのような場合に弁護士に相談したところ、相手の主張に法的な裏付けはないとアドバイスを受け、訴訟を提起して、訴訟を続けていくことで、最終的に支払ってもらうことで和解で解決した。
 債権回収 Q&A
債権回収 Q&A
一覧を見る
- 1. 担保を取っていない場合の債権管理のポイントはどのようなものがありますか?
- 2. 方針決定の流れについて
- 3. 消滅時効の検討
- 4. 差押え対象財産の検討
- 5. 相殺の検討
- 6. 代物弁済の検討
- 7. 債権譲渡による回収
- 8. 交渉①(内容証明郵便による催告)
- 9. 交渉②(支払条件の協議)
- 10. 裁判所を利用した債権回収①(通常訴訟)
- 11. 裁判所を利用した債権回収②(支払督促)
- 12. 裁判所を利用した債権回収③(少額訴訟)
- 13. 裁判所を利用した債権回収④(手形・小切手訴訟)
- 14. 裁判所を利用した債権回収⑤(民事調停)
- 15. 強制執行認諾文言付公正証書
- 16. 保全執行の検討
- 17.「債務名義」取得後の強制執行①(不動産に対する執行)
- 18.「債務名義」取得後の強制執行②(債権に対する執行)
- 19.「債務名義」取得後の強制執行③(動産に対する執行)
- 20. 担保設定による債権回収手続①(抵当権)
- 21. 担保設定による債権回収手続②(根抵当権)
- 22. 担保設定による債権回収手続③(集合債権譲渡担保)
- 23. 民事再生手続き開始の申立ての通知があったら
- 24. 破産手続き受任通知を受領したら