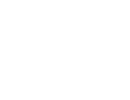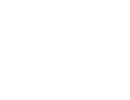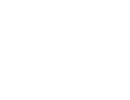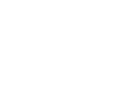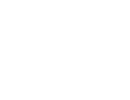借金の返済で月々の生活が大変な場合に、法的整理を利用するなどして、経済的に立ち直ることができます。
「生活費の不足、突発的に現金が必要になった…などの理由から、手軽なキャッシングを利用した結果、多重債務に陥り、返済が追いつかなくなってしまった」という依頼者様に多くお会いしてきました。
そんなときは、債務整理をご相談ください。
債務整理は、借金の総額や依頼者様の収入を考慮して、主に
「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの方法をとります。
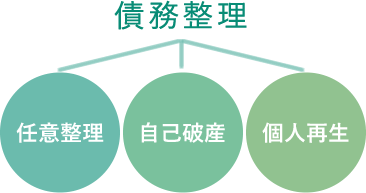
自己破産
借金の総額が依頼者様の収入や資産では返済不可能な場合には自己破産を行います。自己破産は、裁判所に破産の申出を行うとともに免責許可を求める手続です。
破産手続が終了した後で、免責に関する審査を行い、浪費などの免責不許可事由がなければ免責許可の決定が出ます。免責許可決定が出た場合には強制執行を受けることはなくなります。
独身 給与月額20万円程度 住宅は賃貸 借入総額200万円(銀行カードローン、サラ金など)月々の返済8万円の場合
このような場合、住宅の賃料に加えて借金を返済していくと毎月の生活が苦しく、時にお金が足りなくなります。そういった状況のときには自己破産手続きをして免責を得ることで返済をしなくてよくなります。また安定してくれば貯蓄をしていくこともできます。以前のような借金の返済に追われてばかりの生活から立ち直ることができます。
個人再生
個人再生手続きは、借金総額を大幅に減額することができます。この手続きは住宅以外に特に大きな資産がない場合に住宅を残す方法として有効な手続きです。
個人再生手続きが債権者の反対なく認められた場合、住宅を残して、住宅ローンの支払いを続けながら、他の借入金の8割近くを減額できることがあります。
家族4人(夫婦と子ども2人)夫給与月額30万円程度、自宅所有、住宅ローン月10万円返済、残額2000万円、他の借入金700万円(銀行カードローン、キャッシングなど)月々の返済15万円
上記のような状況では、住宅ローンを返済した後、他の借入金の返済を行うと生活費が回りません。このような場合、カードローンなどで返済と借り入れを繰り返して自転車操業になりますが、いずれは資金繰りに行き詰ります。このような場合に個人再生手続きをとることで、住宅を残し、住宅ローンの返済は続けたままで、借入金を140万円ほどまで減額し、毎月の返済額を4万円ほどまでに減額できることがあります。
任意整理
金融機関と交渉をして、リスケ(返済計画の変更)などによって、法的手続を利用せずに借金を返済できます。破産や再生手続を利用せずにすみます。借金の総額が少額で、依頼者様に定期的な収入があり、数年程度で返済可能な場合には任意整理を行います。任意整理は、依頼者様の収入状況を把握し、毎月の弁済可能額を検討したうえで、借金総額を考慮して、毎月の弁済額を決めて、弁護士が個別に貸金業者等と和解交渉を行います。
独身 給与月額20万円程度、自宅は賃貸 借入金100万円(銀行カードローン、キャッシングなど)月々の返済6万円
上記の状況でリボ払いなどの場合は実は返済を続けてもほとんど利息のみで元金がほとんど減りません。そうしたときに任意整理を行い、5年程度の返済を続ければ確実に借金がなくなるように各業者と和解を行います。そうすることで毎月の返済も少なくなり、生活に余裕が生まれます。

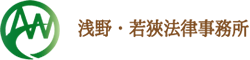
 自己破産 Q&A
自己破産 Q&A